大滝詠一

大滝詠一。本名大瀧榮一。1948年岩手県江刺市に生まれる。コニーフランシスの「カラーに口紅」に衝撃を受け、ポップスに目覚める。早くからテープレコーダーを私的に利用しFEN
(アメリカ 軍極東ラジオ放送網=極東アジア駐在アメリカ軍人向け放送のこと。現在のAFN)を録音しまくり、ポップスの地盤を築いていく。同時期にエルビス・プレスリーと出会いロックンロールの虜となる。高校生になるとビートルズの影響で作曲などを始めるが、始めた当時の曲は加山雄三調だったという(笑)。
大学受験のため上京後、ロックバンド「はっぴいえんど」に参加し1970年プロデビュー。ヴォーカルとソングライティングを経験する。バンド在籍時1972年11月にアルバム『大瀧詠一』でソロデビュー。バンド解散後、1973年自身のレーベル「NIAGARA」を設立。独特の手法で歌謡曲の解釈を行った奔放且つオリジナリティー溢れるアルバムを多数排出し一部にマニアなファンを獲得するも1978年のアルバム『LET'S
ONDO AGAIN』で一旦レーベル活動を休止。しかし、レーベルはレコード会社を移し1981年3月21日に突然アルバム『A
LONG VACATION』で復活。これが当時のチャートで2位になる大ヒット&大ロングセラーを記録。大滝詠一の名前が大きく浸透した瞬間でした。しかし大滝氏自身は沸騰する“大滝熱”をよそにマイペースに活動。84年のアルバム『EACH
TIME』を最後にコンスタントな音源リリースを停止。世間の大滝詠一熱は徐々に冷めて行き一時代を象徴するポップス歌手かマニアにはポップスヒーローとして認識が定着していきました。はっぴいえんどの再評価が徐々に高まるにつれ大滝本人の次回作の要望も高まった97年、14年ぶりにドラマ主題歌としてシングル『幸せな結末』をリリース。大ヒットを記録し大滝健在をアピール。しかしその後のリリースは既発盤の再発事業や単発的なシングル(2003年『恋するふたり』)に終始。現在にいたる。管理人の私がこの方から受けた影響と言うのは計り知れません。入口としては「はっぴいえんど」のメンバーで1番好きな人という事で旧譜を漁り始め、『A
LONG VACATION』に大ショックを受け、以後音楽評論家の萩原健太氏同様に心の中で“師匠”と呼ばせていただく事にするほどでした。彼から受けた物という点では好きな物に対する姿勢、というのが1番大きいと思います。勿論彼のお陰であまり同世代が聴くはずの無いマニアックなオールディーズポップスの良さも理解できるようになったのでありますが、影響と言う点ではこれには敵わないです。彼の自分の興味があるものに対しての徹底したマニアっぷりは多くの人の知れる所で、自分のディスコグラフィを自身で纏めた4500円もする本を出すほどです。そしてここが重要なのですが、彼は“音楽だけ”の人では無いのです。彼は漫画・お笑い・映画・野球という所謂日本の大衆娯楽全般に精通してるのです。それが彼をブライアン・ウィルソンやライブ活動休止後のXTC・アンディパートリッジの様な悲劇的もしくは偏屈なレコーディング・アーティストたらしめず独自のキャラクターを醸し出している要因なのです。彼の音楽はあまりに想像力・解釈力豊かなため、しばしば肉体性の欠如や自己完結型の音楽等とも批判される事がありますが、それこそ本物になることなんであり得ない日本人がやるポピュラーミュージックの醍醐味だと私は思っています。
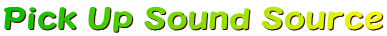
『A LONG VACATION』
1、君は天然色
2、Velvet Motel
3、カナリア諸島にて
4、Pap−Pi−Doo−Bi−Doo−Ba物語
5、我が心のピンボール
6、雨のウェンズデイ
7、スピーチ・バルーン
8、恋するカレン
9、FUN×4
10、さらばシベリア鉄道
1981年3月21日発売。日本音楽史上に残る金字塔。以上。で、終わってもいいんですが、一応書きます。でも今更何を書けばいいのでしょう?ありとあらゆる賛辞が出し尽くされ、この1枚を中心にリゾートミュージックなんてシーンも形成されたりしました。音楽的にみても隙が無く、マニアなリスナーでなくても思い出に残る、この二つを両立する事の如何に難しいことか。少し同世代のリスナーのあり方を不思議に思うとすれば、無駄なコアな音楽やオルタナティヴな音楽に対する評価の高さにあります。そこで出てくるのが本作のキーワードの1つであると通説的に言われる歌謡曲という言葉。歌謡曲、この3文字が日本人がポピュラーミュージックのあり方としてオリジナリティを大いに発揮出来る数少ないフォーマットなのであると思っている私には高すぎるオルタナティヴの評価が少しだけに気になります。しかしそれも当然といえば当然で、このアルバム以降に本気で外来のポピュラーミュージックと歌謡曲を向き合わせた音楽をやっていた人間は目立つ所で山下達郎、桑田佳祐の率いるサザンオールスターズ、佐野元春位だけといってもいい様な状況であったと考えられます。しかし彼らが幾ら完成度の高い楽曲発表しても、もはやメイン市場を獲得したそれではオルタナティヴを求め始めた若者達を満足させられる訳は無く、それらより下の世代はやはり海外のオルタナティヴシーンに目向けるしかなかったのです。そして日本の代表的なオルタナティヴと言えるブラッド・サースティ・ブッチャーズですら未だまともな商業的評価は与えられていない中で、歌謡曲と言うメンタリティを若者の聴く音楽として成立させるにはMr.children辺りまでの敷居低さや文脈の明快さ持たないとならないのです。もはや歌謡曲は気軽な物でなくなってしまった、といえるかも知れませんね。そこで改めて思い知るのが本作の偉大さであり、圧倒的な聴き易さであると思います。ある程度オルタナティヴ・ミュージックが日本チャートものバンドの音として定着し始めた昨今、彼らが皆そろって口にするのが“いい歌”であることへの欲求であります。その参照点としても、非常に重要になるのがこの作品だと思います。歌謡曲が再び日本で大きな流れを作る事があるのかは分かりませんが本作が歌謡曲こそ日本人のミクスチャー感覚に最も合致した音楽のひとつであることを提示した貴重な作品であると言う事は少しもずれる事が無いのです。

『LET 'S ONDO AGAIN』
1、峠の早駕篭(多羅尾伴内楽団)
2、337秒間世界一周(多羅尾伴内楽団)
3、空飛ぶカナヅチ君(宿霧十軒)
4、烏賊酢是!此乃鯉(Each Ohtaki)
5、アン・アン小唄(山形かゑるこ)
6、ピンク・レディー(モンスター)
7、河原の石川五右衛門(オシャマンベ・キャッツ)
8、ハンド・クラッピング音頭(イーハトブ田五三九)
9、禁煙音頭(竜ケ崎宇童)
10、呆阿津怒哀声音頭(蘭越ジミー)
11、Let's Ondo Again(アミーゴ布谷)
12、Let's Ondo Again-’81MIX(アミーゴ布谷)
1978年発表のナイアガラ・フォーリン・スターズ名義のオムニバス作品。ちなみに曲目リストは現行CDの物です。え〜日本で外来のロックなんてのを深く聴くと、よっぽどでなければ行き着くのが「俺はロック的なルーツなんて何処にも無い、ただの日本人なんだ」と言う結論。それは非常に悔しい半面、ある種の開き直りを誘発します。「ルーツなんて無いのが逆に強みなんだ」という開き直りですよね。しかしそれでも「日本人で良かったな」と思わせてくれるアルバムが幾つか存在ます。それは村八分、はっぴいえんど、サニーデイ・サービス、ボアダムスのアルバムだったりする訳ですが、この作品はそれの最高峰の作品に当ります。現行CDにはピーター・バラカン氏が絶賛の寄稿をされ、「アルバムとして日本で1番好きな作品」と言い切っております。管理人の視点ではこれはザ・クラッシュにおける「サンディニスタ!」とほぼ同じ位置にあります。外国の音楽と自国の音楽を自分の尺度でグチャグチャ混ぜ合わせてぶちまけるという奴ですね。ただクラッシュがバンドとしての実験精神の駆り立てるままにを「サンディニスタ!」を作ったのに対し、この作品は大滝詠一氏が自らのレーベルの商業的な失敗続き(この作品は「ロング・ヴァケーション」以前の作品)に対し「こりゃもう、だめだな・・・」という諦めからこの作品は発想されています。この世で何が1番恐ろしいかといえば酸いも甘いも全て経験した大人がキレるのというのが1番恐ろしい訳です。そういう意味では日本最高のパンクアルバムの一枚とも言えるでしょう。まさに無秩序、超アナーキー、あまりのやりたい放題に戦慄が走ります。ロックと歌謡曲というのは大滝氏のはっぴいえんど時代から背負わせられた宿命だったのですが、いわゆる歌謡曲の部分に関してはこの作品までは控えめと言うか遠慮がちだった訳です(だからこそ以前の作品がキチンと評価されているという面もあります)。しかし会社の倒産がほぼ決定している状況でこの作品に向かった日本のフィル・スペクターはキレてしまいました。いわゆる反則技=サンプリングに突っ走るわけです。まだ世界で初めてサンプリング・ミュージックを完成させたYMOすらサンプラーを開発させていない時期にサンプリングに走った訳です。もちろん人力サンプリングですから、いわゆるパクリですよね(笑)。一見分からないかも知れませんがこのアルバムの8割以上はカヴァーで(セルフカヴァーも含む)、他人の曲のカヴァーはかなり好き放題してやっています(特に歌詞)。カヴァーやサンプリングのネタを一々解説してると日が暮れてしまいますので解説は割愛しますが、これの元ネタが全て理解できた時恐らくポピュラーミュージックの本質と言うものに一歩近づいたような気がするでしょう(少なくとも私はそう思いました)。それだけ濃い情報量が詰まっていながらこのアルバムの質感は非常に明るくて(まぁキレてますから)笑いに満ちたものになっています。そういえば音楽評論家の湯浅学氏は来日したジョー・ストラマーにこのアルバムを「これは日本の民謡ロックだ」と言って渡したそうです。しかしそれだけのハードコア具合(音ではなく情報のハードコア)と言うのが災いしてアルバムのセールスは発表当時大滝詠一史上最悪のものに終わりました(本人によると500人程度しか聴いてないのでは?とか)。結果的に大滝詠一はロンバケでブレイク後も日本のオルタナティヴとして有り続けますが、このアルバムこそ大滝詠一が日本最高のオルタナティヴ・ミュージシャンの一人である決定的な証拠であるのです。

