The Pop Group
The Pop Group。1977年イギリスのブリストルで結成。結成当時のメンバーはまだ高校生だったという。メンバーはマーク・スチュアート(vo)、ギャレス・セイガー(g,sax)、ブルース・スミス(ds)、ジョン・ワディソン(g)、サイモン・アンダーウッド(b)の5人。いわゆるパンク・ムーヴメントに触発されバンドを結成。サウンド自体は速い16ビートのスリーコードパンクではなくポストパンクならではのエクスペリメンタル・アヴァンギャルドミュージックといったほうが正しい。メンバーにサックスが居ることでも分かるように基本的にR&Bやファンク、特にジェイムス・ブラウンやフリージャズの代名詞オーネットコールマン(コールマンは後期フリージャズファンクを志向した)や成り立ちが似ているという点でオリジナルパンクスに愛好されていたレゲエ、特にダブという手法で料理された音楽の影響が濃厚なメロディよりもグルーヴ重視のサウンドを展開する。元々ポストパンクの同僚であるワイヤー並に楽器の弾けなかったこのバンドはパンクスならではの怒り・激情・勢いを表す事により独自のサウンドを奏でる事に成功。同時代で言うとジェームス・チャンス&コントーションズ辺りにも共振していると言えるであろう。しかしこういったアヴァンギャルドなバンドには良くある事で、あまりに過激な政治的主張を続けたため市場にはほとんど受けいれられなかった。しかも上の写真のようにメンバー同士の結束や音楽的趣向も解散まで終始あらぬ方向向いたまま、オリジナルアルバム2枚を出しバンドは早くも分裂。ギリギリ体勢を保ちつつ1枚の編集盤を出して解散。後に1枚の編集盤が出されたが、現在CDでは1stアルバムの「Y」以外は全て廃盤であり、権利関係も複雑且つ解散時よりのメンバー間不和により再発は難しいといわれてる。我国日本ではこうしたアヴァンギャルド・ミュージックの評価は一定して高く(NYパンクの名盤である「NO
NEW YORK」も日本が世界初CD化させた)、近年で言うと山本精一率いる馬鹿テクインストバンド・ROVOがカヴァーをしたり、向井秀徳などがナンバーガール後期に大胆にこのバンドのダブ・ファンクなサウンドを取り入れてみたりとアンダーグラウンド寄りの人脈から支持は常に熱い。こういう現象を見て僕は、日本はポップミュージックをやるには最低の国だけど、ポップミュージックを聴くには最高の国なんじゃないか、という気さえしてくるのである。

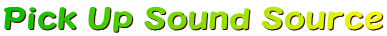
『Y』
1、She Is Beyond Good and Evil(Bonus Track)
2、Thief on Fire
3、Snow Girl
4、Blood Money
5、We Are Time
6、Savage Sea
7、Words Disobey Me
8、Don't Call Me Pain
9、The Boys from Brazil
10、Don't Sell Your Dreams
1979年発売の1stアルバム。現在正規ルートでポップグループ神話を体験できるのはこれ一枚である。96年発売の現行CDにはファーストシングルで名曲の誉れ高い「She
Is Beyond Good and Evil」を収録したものになる。管理人は当然96年に出たこのCDが初体験なので特に違和感は無い。この曲は一生懸命ファンクしようとしてるがかなり強張った緊張感溢れるような物になっている。特に本来ファンクならさりげなく粘るように演奏されるはずのギターカッティングを恐ろしくガチガチに分断し強調する事によって異常な切迫感を生み出している。その上に載る切れ気味のヴォーカル&サックスがこの曲を加速させ唯一無二の楽曲として成立させている。これは名曲というしかないだろう。そして本編スタートのM2は割りと切れの良かったM1に対し、冒頭から空間を捻じ曲げようとするかのような音像がグワッっと広がる。その音像の中から獣の呻きのような声が聴こえ突然凄まじく太いベースとカリカリと神経質なギターカッティングが入って来る。この曲で白眉なのはブルースのドラムとプロデューサーであるデニス・ボーヴェルの手腕である。ブルースのドラムは無茶苦茶に掻き鳴らされるギターと好き放題がなり続けるヴォーカル、割りと同じ様なフレーズをかなで続けるベースをまとめ上げグルーヴに昇華している。そしてデニスは曲中漂流しつづけるサックスに負けないぐらいの強烈なダブ処理を施し、一歩間違えたらバラバラになりそうな曲を完全に一つしている。確かに稀有な才能の持ち主であるマーク・スチュアートの存在も忘れてはならないがこの曲を象徴としアルバム全編フリージャズやファンク、レゲエ・ダブなどを技術そっちのけで貧欲に、しかもパンク的な圧倒的なテンションで消化しようとしたバンドの意志を何とか実現しているのがこの二人の力量といえるだろう。歌詞も他のパンクとは一味違った加害者意識、現状起きてる悲劇に対し見て見ぬ振りする者は全員悪であるとでも言うような、過剰なまでに言ってる側と言われてる側両方共に罪の意識を植え付けるような物である。勿論これら全てが成功しているわけでなく、怒涛のバンド最高傑作である次作と比べてしまうとあまりに未整理な部分やまだまだ頭でっかちな部分もかなり多く残っているのも事実だと思う。しかし本盤がパンクの名盤と呼ばれるのはこうまでして現状に立ち向かい、行動を起こした熱き若者の初期衝動が余すことなく音に現れているからである。そうした血と闘争の刻印とでも呼ぶべきこのアルバムは永遠に若者たちを鼓舞していくだろう。ちなみに『Y』とは「Why?」のことだという(「レコードコレクターズ20周年ニュースタンダード」より抜粋)。

『For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?』
1、Forces of Oppression
2、Feed the Hungry
3、One Out of Many
4、Blind Faith
5、How Much Longer
6、Justice
7、There Are No Spectators
8、Communicate
9、Rob A Bank
1979年10月の2枚目のシングル「We Are All Prostitutes」(超名曲。今はラフトレードのコンピかなんかで聴ける)を挟んで1980年3月に発売された2枚目のアルバム。まずこのタイトル。「我々は一体どこまで大量殺戮を見逃さなくてはならないんだ?」といった強烈な投げかけ、焦燥感が滲み出てしまっている。ラフトレードへの移籍によって前作で大活躍だったプロデューサー、デニス・ボーヴェルの力は借りられなくなったので本作は前作に比べ空間たっぷりのダブ処理やジャズっぽいピアノを聴かせていたのに対し、バンド自体の余裕の無さとバンド本来の主張が合致したハードコア・フリージャズファンクなサウンドと化した。初回盤LPには数枚のペーパーが付き、その中にはABBAとビートルズをおちょくってコラージュした写真に「FREEDOM
IS NOT ESCAPISM(自由は現実逃避なんかじゃない)」と殴り書きされたものもあったそうだ。内容は1曲目からとにかく疾走感が凄さまじい。ケチャがコラージュされたイントロが終わるとファズかけすぎのベースがリフを弾き、軋みまくったカッティングを鳴らすギターとフリーキーでノイジーなギター二つが縦横無尽に駆け巡る。間奏からはサックスの吹き方をしてないサックスも入ってきてもう大変(笑)。マーク・スチュアートの絶叫もやまずまるで本当のジャズのように出尽くしたような感じで終わる。ジャズは10分以上やってこういう終わり方をする物だが、このバンドの場合それも2分半だ(笑)。M3になると今度はラップ(?)だ。妖しげなピアノループにマークの珍しく落ち着いたヴォーカルが韻を踏みまくる。変な曲(笑)これも一分強で終わってしまう。続くM4が凄まじい。珍しくベースとドラムがやけに前面に出た曲だな、なんて思ってると大間違い。途中からM1で鳴っていたのより遥かにノイジーなギターがギャーピー炸裂しまくり。とにかくこのバンドのサックスとリード・ギターは全く脈絡が無い。その分オーソドックスにファンクやレゲエのリズムを咀嚼したベースやドラムが印象に残るから不思議なバンドだ。M5になると割と前作の延長上の空間のあるダブサウンドが聴けるが、その筋のプロだったデニスのダブ処理に比べると明らかに粗いし、表現がハードコア化している。M8は今作ではどこか飛び道具感のあるサックスが全編吹きまくられる。サックスやギターは相変わらず変だがここではベースまでも狂ってきている。もうここで唯一平静を保ってなんとか踏ん張っているドラムのブルースにはマジで同情する。最後のM9は冒頭から全編フューチャーされるコーラスがちょっとクラッシュみたいで(クラッシュファンに怒られるかな?)、アルバム中1番まともな構成をもった曲だ。いざまともな曲をやられてみると、なんとなく面白く無いのはリスナーの我侭だろうか。ただここらへんにバンド解散の影が出てるかもしれない。しかし完全に曲の途中のカットアウトでアルバム終わるかよ、普通(笑)。このアルバムの後バンドは完全に分裂。契約の関係からか、アウトテイクやライブ音源を纏めたレア音源集を出してバンドは正式に解散に至っている。

