羅針盤

羅針盤は1988年に結成。オリジナルメンバーは山本精一(vo,g)、須原敬三(b)、伴野健(ds)、吉田正幸(ky)の4人。羅針盤のソングライターは日本で数少ないオルタナティヴと言う動きにリアルタイムで共振し、シーンの一部を担ったボアダムスのギタリストで“関西の鬼才”こと山本精一です。羅針盤はその多彩な経歴を持つ山本精一が「ポップスがやりたい」と結成したバンドです。上の写真は4枚目のアルバム「はじまり」が発売された頃のもので須原・伴野が抜け、柴田(b)・チャイナ(ds)に加入した当時のものになります。羅針盤の音の特徴としてはそれまでボアダムスで奇声やノイズギターを、想い出波止場などでエグいクラウト・ロック、ニューウェーヴ、プログレ趣味を発露し続けてきた山本精一がはじめて打ち出したポップスと言われています。基本的にソフト・ロックやフォーク・ロック、アシッド・フォークなどのテクスチャーが見え隠れするものの、それだけで語ることは不可能で一筋縄ではいかない山本精一らしい音楽とも言えるでしょう。音の感触としては耳に痛くないエレキ、アコースティック・ギター、キーボードの響きにダンサブルなビートを刻むドラムスが不思議と共存するキラキラしたポップミュージックです。空間を意識したような音作りやエコーの掛かり具合などにいわゆる“音響派”といわれるようなサウンドトリートメントをいち早く歌ものポップスの領域に持ち込んだバンド、とも言われております。といっても羅針盤の核はそういった音の処理より山本精一の「歌声」と「歌詞」に尽きるでしょう。この現代社会を生きていく上で必ず感じたことがあるのではないかと思われるような本質的な疑問や諦め、それに相反するように湧き出てくるかすかな希望を乗せた歌詞。それがファルセットで優しく歌われるのです。こういった要素を考えても羅針盤と言うバンドの曲はNHKの「みんなのうた」あたりでも流れてても全くおかしくないです。ちなみに現在(2004年4月)までに羅針盤は6枚のフル・アルバム、1枚のミニ・アルバム、2枚のシングルを発売しており(この他にライヴ会場などではライヴCD-Rを何作も発売している模様。そういう意味ではグレイトフルデッドっぽい)、その全てが名盤という恐ろしいバンドです(まぁ主観ではありますが)。近作での歌詞はデビュー当時より更に本質へ向かい、宗教的な領域にまで踏み込んでいるのではないかと思わせるほどです。そして、来る2004年7月には9ヶ月ぶりで早くも新作が発売される予定である。
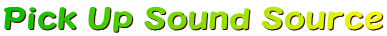
『らご』
1、永遠のうた
2、クッキー
3、HOWLING SUN ―philgrim's progress―
4、FLAT
5、かえりのうた
6、ライフワークス
7、いのち
8、生まれかわるところが
1997年発売の羅針盤のデビューアルバム。インディーで発売された後、メジャーへ移行しシングル「永遠のうた」が先行カットされ、ジャケット変更の後に発売されたと言う経緯をもつ。このアルバムは1曲目で先行カットされた「永遠のうた」に尽きると思います。他の曲も悪くないですが(管理人はM3、5、7が好き)、ちょっとこの曲が頭四つ位抜けていしまっていて他の曲が少しプログレっぽかったりと、まだ羅針盤と言うバンドコンセプトを模索してるような楽曲に聴こえてしまいます。しかしこの「永遠のうた」は今風に言えば羅針盤にとってのマニュフェストソングであると言えます。上に書いたよう羅針盤の根本をなすキラキラしたサウンドメイキングと本質的な歌詞。“だから 聴いてくれ 何も特別なことなんかじゃないと”など山本精一が羅針盤をどういう風に見せていきたいか、聴かせて行きたいかがこの曲に込められています。曲のオーラスではピアノが急に出てきて転調し英語であらゆる単語に“ANY”が付けられた歌詞に山本自身の声で「ラ〜ララ〜ララ〜」とコーラスが付けられリスナーは幸せ一杯な気分になってしまうでしょう。この1曲だけで名盤の価値がありますので質感の良いポップスをお探しの方は是非。必聴。
『せいか』
1、せいか
2、アコースティック
3、クールダウン
4、光の手
5、朝うたう夜のうた
6、ドライバー
7、カラーズ
8、おわりの鈴
1998年発売の2ndアルバム。まずジャケがとんでもなく可愛い。あまりの可愛さにはじめて見たとき少し悶えてしまった(笑)前作でフォークを基調とした都市ポップスに接近するようなメロディーにプログレチックなエコー処理と所謂80年代インディというか初期ラフトレード的な清涼感のあるエレキ&アコースティックギターサウンドをのせるという方法論を示した羅針盤。この2ndはその方法論が確立し、進むべき方向をガッチリ掴んだ名作です。その他にもう1つ注目すべき点として歌詞に大きな変化が見られます。1stではどこか生命そのものを歌ったものが多かったが、ここではその生命がどう生きていくのか、生きるってどういうことなのか、という以降羅針盤が追求していく事になる終りのないテーマへと辿り着きます。1曲目の冒頭は「永遠のうた」の続きを意識したかのような「ラ〜ララ〜」という歌い出しからファンは「やられた!」とお腹を見せて降参してしまうでしょう(犬かよ)。羅針盤がジェリーガルシア率いるグレイトフル・デッドなどのジャムバンドとよく比較されるのはこういったキラキラした楽曲にいつ終わるとも知れないジャムを挟み込む構成的な緩さというか余裕を持たせているからだろう。2曲目は1曲目の豪華なサウンドから一転アコースティックサウンドへ。優しいメロディにふわふわした山本精一のファルセットが気持ちよい羅針盤ならではの曲。続く3曲目はなんだか運動会でも始まってしまいそうな軽快な歌で始まり、それが一旦ブレイクに入ると一気にスペイシーな展開へ。ここらへんはボアダムスやROVO活動が徐々に羅針盤へフィードバックされていることが分かる。4曲目になるとROVOのメンバー勝井祐司のヴァイオリンが入る。ザ・バンドのようなタイトなバンドサウンドが珍しい曲。5曲目は、その後の7曲もそうなのだがポストロックや音響派な音処理が目立つ作品。7曲目なんかシー・アンド・ケイクの曲だといわれても気付かないぐらい。こういった音が平然と内包されていることで羅針盤は一時期“音響フォーク”と呼ばれた事もあるそうだ。最後の曲になると暖かいキーボードとアコースティックギターの素朴なサウンドが実に豊に聴かせる。歌詞にも「沸きあがるメロディー
たったひとつ それだけで きっと見える ずっと遠く」とされ、一見羅針盤の多彩なサウンドからすると矛盾しているようだけど、やっぱり羅針盤が目指しているのはそこだと思う。こうつらつらと書かれてる文章なんかさっさと全て忘れて真っ白な頭で聴いて頂きたい名作です。

