The Band
The Band。メンバーはロビー・ロバートソン(g)、リック・ダンコ(b、vo)、リヴォン・ヘルム(ds,vo)、ガース・ハドソン(ky)、、リチャード・マニュエル(ky,vo)の5人。1968年アルバム「Music From Big Pink」でデビュー。77年までオリジナルメンバーで活躍し、オリジナルアルバムを9枚(ライヴ盤を含む)を発表し解散、後にロビー・ロバートソン無しで再編成などをしてたりする。メンバーはデビュー以前にカナダのスター、ロニー・ホーキンスのバックバンドやボブ・ディランのバックバンドに「ザ・ホークス」として活躍。特に後者での活躍が多いに認められデビューへ至る。このバンドの音としてはとにかくアメリカ南部のブルース、R&Bをこれでもかというほど煮詰めてその最良部だけを抽出したかのようなサウンドで、いわゆるギターがガーン、ドラムがバッシャーン!ヴォーカルがギャー!という価値観とは真逆に位置するサウンドです。こうしたアメリカのブルースを下敷きにした独特のサウンドを奏でていながらもメンバー5人中カナダ人が4人でアメリカ人が1人しかいないこともあって彼らは“よそものブルース”とも言われました。しかしそういったブルースに真摯な姿勢は同業者、すなわちミュージシャンに物凄い影響力があり、例えて言えば当時クリームで活躍中だったかのエリック・クラプトンがアメリカツアー中に彼らに出会い「もう自分はこんなバカなこと(ハード・ロック的な音や延々続くインプロ)は辞めるべきだ」と発言したそうです。一瞬耳に入る音ととしてははかなり地味で渋い方に入るということで管理人の私も彼らの1stアルバムを買って「失敗したかな・・・」と思ってました。しかし半年位寝かせた後また聴いてみるとこれがとんでもなく良いということに気付きました。おそらく彼らの1・2枚目は自分の生涯ベストアルバムでも間違いなくTOP10入りするアルバムです。しかしこれほど好きなのに何故か僕はこのバンドの好きなところがイマイチ上手く説明出来ません。ヴォーカルの渋く切ないハーモニー、じっくりと暖めていくようなバンドグルーヴ、各楽器の革新的で奇妙な鳴リetc。と彼らの良い所を挙げれば切りが無いのですがどれも自分がこのバンドを好きな感覚と合致しません。恐らく彼らの出している空気感のようなものが気に入ったのではないかと自分では考えております。
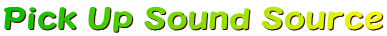
『Music From Big Pink』
1,Tears of Rage
2,To Kingdom Come
3,In a Station
4,Caledonia Mission
5,The Weight
6,We Can Talk
7,Long Black Veil
8,Lonesome Suzie
9,This Wheel's on Fire
10,I Shall Be Released
1968年に発売されたThe Bandの歴史的名盤兼デビューアルバム。上に書いたようにザ・バンド面々はボブ・ディランのバックバンドで名を上げて行きました。既にバンドとしてのキャリアは十分すぎるほどあった彼らようやく巡って来た自分達名義のアルバム発売。それはもはやデビューにして10年目のぶどう酒のような芳醇な味わい。最初の1曲目から歌詞の内容が「娘が俺の言う事を聞いてくれない」と安酒場で飲んだくれる親父を描いた名曲「怒りの涙」から激渋な仕上がり。アルバムは終わりのボブ・ディランのカヴァーである「I
Shall Be Released」まで全編所々で炸裂する必殺キーボード、タイトなのか緩いのか分かりにくいドラムス、意外と良く聴くと奇妙な響きを持ったギター、そして何ともいえない味わいのハーモニーで哀愁を誘います。歌詞の内容もボブ・ディランが関わっているせいもあってか人間の、ひいては男の業みたいなものを強く想起させます。振られた女に対して吐き捨てる、もしくはもう一度戻って来いと女々しく歌い上げる本物のブルースの曲より僕としてはより強い共感を得られます。本来なら1曲1曲色々と書いていこうと思うのですが、ちょっと言葉が思い浮かばないです。僕の場合好き名盤でも色々言いたくなる名盤と問答無用の名盤があって間違いなくこれは後者に当たります。とにかくこのアルバムを少なくとも10回は聴いてピンと来なければこっち方面に縁が無かったということなので諦めてください(笑)。僕はそうじゃないのですが恐らくグランジを通過した人にとっては究極のスルメアルバムとも言えると思います。
『The Band』
1、Across the Great Divide
2、Rag Mama Rag
3、The Night They Drove Old Dixie Down
4、When You Awake
5、Up on Cripple Creek
6、Whispering Pines
7、Jemina Surrender
8、Rockin' Chair
9、Look Out Cleveland
10、Jawbone
11、The Unfaithful Servant
12、King Harvest (Has Surely Come)
1969年発売の2ndアルバム。ザ・バンドが登場した当時はサマー・オブ・ラヴと称されるサイケデリック・ムーヴメント(厳密には67年ごろ始まる)の影響によって中産階級の若者はハッパやLSDを呷りながら頭に花を飾り、既成概念に捕らわれない服装をし、セックスを筆頭にあらゆる物に対して自由を求める風潮が隆盛を極めていました。音楽も当時はその全てを解放せんとするこのムーヴメントに追い討ちをかけるかのように逆回転エフェクトや妙なSEの入った既成概念を打ち破らんとする物が多く生み出されました。その代表例がビートルズの「サージェント・ペパー」であり、ピンクフロイドの1stであり、トゥモロウの1stアルバムだったりしたわけです。一方でロックの先頭に立っていたボブ・ディランは66年に大事故に巻き込まれてこのムーヴメントに遅れをとる形になります。そうして薬物の酩酊感から覚めたディランは自らのルーツ、ロックンロールのルーツをもう一度見つめなおすためにザ・バンドと共に地下に潜ります。地下に潜ったディランとザ・バンドの面々はフォークやカントリー、ブルーズ、R&Bをグツグツ煮詰めるようなセッションに明け暮れるようになります。その成果がディランの67年のアルバム『ジョン・ウェズリー・ハーディング』だったり、このザ・バンドの1stアルバムだったりしたわけです。1stアルバムからリスナーはもとよりミュージシャンに大きな絶賛を浴びていたのはそのサイケデリックムーヴメントに対抗し、アメリカの伝統音楽をロックのイデオムの中に取り込むことに成功していたことが大きかったのです。このカナダ人4人アメリカ南部人1人によって構成されるバンドの音楽は、当時ロックを我が物顔で奏でていたイギリスに向けてハッキリと“ロックンロールはアメリカの音楽で、イギリスを筆頭としたロックミュージックはそれを搾取したに過ぎないんだ”という事実を痛烈に伝えます。それはただ快楽を求めていたミュージシャンやリスナーを批判する部分もあります。そうした部分はザ・バンド本人たちに突き刺さる部分でもあり、サイケだのなんだのと生きる事の厳しさから逃れようとする中産階級の若者に当てられた痛烈なメッセージだったのかもしれません。その姿勢が作品として結実し、バンドの勢いが完全に沸点を迎えたのがこの作品です。一聴するとこの作品はなんて地味なんだ、とも言えるかもしれません。美しいメロディが沢山あるわけでもなく、ノイジーなギターによって得られるスリリングな快楽は皆無、うっとりするようなコーラスワークも無し。というとまるでダメなアルバムのようですが、このアルバムはロックンロールのルーツを炙り出す事によってそういう既成のロックミュージック的な価値基準をかなり批判しています。このアルバム魅力とはアメリカ南部の黒人音楽のような粘りや魂(ソウル)の表出であり、アメリカの伝統的白人音楽(フォーク、カントリー)の安らぎであるのです。リック・ダンコ、リチャード・マニュエルのヴォーカルはどうしようもなく土臭く切なく響き、レボン・ヘルムのキックとスネアは木の温もりが感じられます。ガース・ハドソンの鍵盤系のプレイも時々凄まじいリフを弾いたり、バラードでの叙情的な味わい絶妙にサポートしています。ギタリストのロビー・ロバートソンも本来はジミ・ヘンドリクスもビックリのハードでノイジーなブルーズギターを弾いていたこともあるそうですが、ここではエフェクターを一切使用せず、極少の音量でソロさえ殆ど取らず歌の裏で絶妙なバッキングやオブリガードを弾きまくります。山本精一にこのロビーのギターはXTCのアンディ・パートリッジ並に革新的だといわせるほどエフェクティヴなギターです。そうした保守的な面と革新的な面が共存するこのアルバムは恐らくロックンロールと白人、ロックンロールとアメリカの関わりという点を見つめていくに当って史上最も重要なアルバムと言えるのではないでしょうか。ザ・バンドの音楽はバンドのアプローチの仕方や作品にしてもそうですが、リスナーの黒人音楽や伝統音楽への興味を試すような面があります。このバンドの音楽によってその扉が開くか、硬く閉ざしてしまうかはあなた次第なのです。