The Velvet Underground

The Velvet Underground。結成は1965年夏。オリジナルメンバーはルー・リード(vo,g)、ジョン・ケイル(vo,ヴィオラ,b,ky)、スターリング・モリスン(g)、モーリン・タッカー(ds,per)の4人。実はこのメンバーはキチンとThe
Velvet Undergroundと名乗るようになってからのメンバーで、モーリンは母体のバンド“Primitives”時のドラマーであるアンガス・マクリースの脱退によって招聘された急造ドラマーである。バンド自体は途中ケイルの脱退やタグ・ユールの参加、モーリンの出産休暇などを挟みながらも4枚の“NYクラシック・ロックアルバム”を残し解散。活動当時セールス的に評価を受ける事は全く無かったが、革新的なサウンドとリリックによって大きな再評価がなされ、永遠に人々の記憶に残る事が許された数奇な運命を辿ったバンドです。The
Velvet Undergroundのサウンドの何処が革新的だったかというと、基本は当時のラヴやエレクトリック・プリューンズなんかにもあったザラザラしたエレクトリック・ガレージサウンドですが、このバンドが特別だったのはルー・リードによる美しいメロディにのせたフォーク的な側面も持ち合わせつつもボブ・ディランにも無い生々しく殺伐としたNYの情景を浮かび上がらせる平熱を帯びた独特のストーリーテリングと、ケイルの音響的な実験精神がぶつかり合うことによって生まれる美と混沌(カオス)が渦巻く全く新しいロックンロールサウンドを発していた点であります。さて、成り立ちから解散まで何から何までドラマティックなこのバンドを語るときに外せないメンバー以外の人間が3人ほどいる。それはこのバンドの才能にいち早く気付きパトロンになった近代アート界の鬼才であるアンディ・ウォーホル、奇妙な運命によってバンドと行動をともにするようになるニコ(vo)、そして音楽的プロデューサーであるトム・ウィルソンの3人。結果的にウォーホルは自分の企画したディスコで演奏するバンドのためにアルバム制作費を工面し、あの“バナナ・ジャケット”を手がけたに過ぎない。しかしバンドとウォーホルの組み合わせはNY=ロックとアートの街と言うイメージを確立。そしてボブ・ディランの進言によりNYに進出しウォーホル一派の人間の誘いでバンドを従えて歌うことになるドイツの歌姫であったニコは、このバンドが不思議と内包していたロマンティシズムを浮かび上がらせるに一役買った。そしてプロデューサーのトム・ウィルスンは当時からボブ・ディランやサイモン&ガーファンクルなどを手がけている名プロデューサーである。ウィルスンは新しい物が生まれる瞬間にしか興味が無い、というのが身上らしくこのバンドを手がける事に。1stアルバムにおける馴染みやすいフォークロック的質感をだすのに大いに貢献した人物。彼等の3人とバンドの4人を主とした思惑によって形成されているバンドのドラマというのがなんともミステリアスで魅力的。これはこのバンドを聴くに当っての大きな魅力の1つと言えるでしょう。そしてこの“7人”によってNY、いや東海岸の確実にバックボーンに垣間見せながら常に前進していく音楽の姿勢と言うのが決定付けられるのであります。今日のロックメディアの過剰なまでの肥大化、というのは商業的な部分は別として、やはり第2のVelvet
Undergroundを作ってはならないという思いも多少はあるのかな、と思う今日此の頃であります。
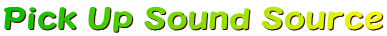
『The Velvet Underground&Nico』
1、Sunday Morning
2、I'm Waiting For The Man
3、Femme Fatale
4、Venus In Furs
5、Run Run Run
6、All Tomorrow's Parties
7、Heroin
8、There She Goes Again
9、I'll Be Your Mirror
10、The Black Angel's Death Song
11、European Son
1967年発売の1st。当時、ドアーズやティム・バックリー、ラブなどを擁したゲテモノレーベル・エレクトラさえ契約を断ったと言われるこのバンドは、パトロンのアンディ・ウォーホル一派のポール・モリッシーの提案により急遽ドイツの歌手であるニコ加入を了承せざるを得なくなる。そしてなんとかMGM傘下のヴァーヴ(ジャズ専門レーベル)と契約するに至った。しかし何が幸いするか分からないもので、この歌手の加入は殺伐とした轟音ロックンロールを鳴らしていたこのバンドの内包していたロマンティシズムを炙り出す事になった。そのロマンティシズムと轟音を筆頭とする様々な二律背反要素の混在こそこのアルバムの“肝”である。更にこのアルバムはNYとロック、アートとロックの関わりあいを如実に現した歴史上最初の一枚といえる。だからこそこのアルバム評価は何処までも拡大し、悪しきスノッブ共のBGMとしても機能してしまうのである。アルバムの内容はというとM1からこのバンドを象徴するかのようなルーの気だるいヴォーカルに深めのエコーがかけられ美しいメロディーが綴られる信じられないぐらいロマンティックな一曲だ。しかし歌詞はもうすでにルー・リード節炸裂である。しかしこのルー・リード独特の一人称が頻繁に出てきてもどこか別の場所で定点観察してるかのようなヒンヤリした熱さの気持ち良さに触れてしまったら、もはや普通の歌詞に感動するは難しい。M2もとんでもない名曲だ。ガレージ風のザラザラしたコードカッティングにルーによる薬物売人の物語を諦観しきったヴォーカルが時折メロディに目配せしながら綴られる稀代のロックンロールナンバーだ。M3になるとニコが初登場。これがクリアなエレクトリックギターにタンバリン、ピアノという簡素なバッキングだがメランコリックな曲調からか混沌とした前曲と次の曲との間に挟まれて絶妙のアクセントとなっている。M4は“靴をお舐め”と綴られるSMを題材にしたエロティックな歌詞がゆったりとルーのヴォーカルによって綴られ、その上にケイルのエレクトリック・ヴィオラが終始炸裂する非西洋音楽的な響きを醸しだす名曲。M5は軽快なんだか軽快じゃないのか解釈の難しい一曲。一応ギターソロなんかも織り込まれて1番ロックっぽい楽曲構成をしている。M6はニコのヴォーカルによる名曲。この曲も前曲もそうだが、このアルバムは特にジョン・ケイルの音響的な意図からかシンプルなバッキングの曲であってさえもかなりサイケデリックな音像をかもし出している。この曲の歌詞はヴェルヴェッツにおけるルー独特の平熱描写に加え1ミリの優しさが滲み出た数少ない曲だ。M7はタイトルからも分かるようにドラッグのことを歌った名曲。ドラッグを自らの体に注入し、体の変調を事細かに綴る。テンポが変化するルーのヴォーカルとドラムは脈拍を現してるかのようだ。M8になるとかなり明るい曲調になる。コーラスやギターの絡みなどはバンドの最終作『ローデッド』でみせる破れかぶれなルーのポップセンスが既にここに現れている。M9はこのアルバム最後のニコのヴォーカル曲。美しく牧歌的な曲調だが、この曲のヴォーカルをめぐってルーとニコの間で熾烈な駆け引きがあったそうだ。結果ニコがヴォーカルを取る事になったが、ただでさえニコの加入にルーは乗り気ではなかったから、この一軒をキッカケにニコをバンドから早々に追い出すことを考え始めたのであろう。M10はルーとジョンの共作。ここでもケイルのヴィオラが響き渡るルーのトーキング・ブルース風ナンバー。詞も曲に入り込んでいれば鳥肌が立つようなものだが、ふと冷静にみてみるとかなり気味が悪い。ドサ周り時代「こんな気味の悪い曲をまたやったらこのクラブはクビだ」と言われたらしい。勿論バンドは大轟音でこの曲をやって見事クラブをクビになったらしいが(笑)最後M11はジャリジャリとベースが立ち上がる後の「Sister
Ray」にも通じる激ノイジーなエレキ掻き鳴らしナンバー。1曲目の美しさとこの最終曲の対比は今聴いても鮮やかで、見事としか言いようが無い。以上全11曲。このアルバムによってヴェルヴェッツはレッド・ツェッペリンよりも早くロックンロールから逸脱した“ロック”を生み出し、永遠に存在し続けることを許されたのです。ちなみにジャケットの画像は2002年に発売された「デラックス・エディション」です。この「デラックス〜」には現行盤のステレオミックスではなく、モノラル・ミックスがフル収録されています。本作は本来モノラルを想定して製作されているので、是非コレクションは廉価な現行盤ではなくこの「デラックス・エディション」をお薦めします。かなり違った味わいですよ。(2004年8月26日)

