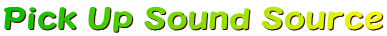The Who

The Whoはロジャー・ダルトリー(vo)、ピート・タウンゼント(g)、ジョン・エントウィッスル(b)、キース・ムーン(ds)の4人からなるイギリスはロンドンのモッズシーンを足がかりにして大メジャーへ突き抜けたロック・バンドです。バンド自体は62年に結成。メインソングライターはピート・タウンゼントで他のメンバーも積極的に作曲をするようになります。バンドはマネージメントの要求により名前を改名させられハイ・ナンバーズとして1964年7月「I'm
The Face」でシングルデビューを飾っていますが鳴かず飛ばずの結果(一説によると500枚程度しか売れなかったと言う話もある)。そして再び名前をフーに戻して65年1月「I
Can't Explain」で再デビュー。これが全英8位の大ヒットしてバンドは軌道に乗りました。以降はバンドは30枚近く(編集盤やライブ盤を含む)の作品を産み落とし、尚且つ現役です。彼らが革新的だったのはまずサウンドに破壊力があったこと。全員モッズを意識したワイルドなR&Bがプレイの下地としてありつつ繰り出されるのがピートのフィードバックを多用したギターサウンド、ジョンの自己主張の強いベースプレイ、竜巻のようなキースのドラム。これらが生み出すグルーヴが何より驚異的であったと思います。そしてもう一つはメロディ。バンドグルーヴに関しては肉薄するバンドは他にも多少名前は思い浮かびますがピート・タウンゼントの様なポップソングライターがいたケースは皆無です。そして最後はそうして出来上がった重量級の破壊力を持ったポップソングに乗せられる歌詞。BeatlesやRolling Stonesが好きな女のことや、ふられた女のことばかりををまだ歌っていた時代に、俺・もしくは俺たちや世代間の軋轢を歌ったのです。この3つの要素は後に起こるパンク・ムーヴメントにまで大きな影響を及ぼす事になります。そして実はこんなこと書くのは非常にコアなファンの方から反感を買うかもしれませんが、私がザ・フーのアルバムで常に聴き続け、これから一生聴き続ける事になるだろうと思っているアルバムはデビューアルバムと、続く2枚目、そして決定的2枚組みコンピレーションの「The
Ultimate Collection」だけです(汗)。それ以外でコネクト出来るのは「オッズ・アンド・ソッズ」や「ライブ・アット・リーズ」位です。そんな人間が書くレビューですのであんまり気にしないで下さい(笑)。そういった僕のザ・フー観を見てすぐわかるように僕にとってザ・フーとは後にも先にも「R&B経由のワイルドでポップなロックンロールを鳴らすバンド」であると言う事なのです。
『My Generation』
1、Out on the Street
2、I Don't Mind
3、The Good's Gone
4、La-La-La Lies
5、Much Too Much
6、My Generation
7、The Kids Are Alright
8、Please, Please, Please
9、It's Not True
10、I'm a Man
11、A Legal Matter
12、The Ox
13、Circles
1965年12月発売。同年1月・4月・11月に出したシングルの成功を受けて製作されたザ・フーの1stアルバム。これが歴史的名盤。それまでのシングルの勢いを全部飲み込みこれでもかと言うほどのエネルギーを詰め込んだアルバムで、商業的にも新人には厳しいクリスマス商戦において堂々の全英5位という成功をも手中にしたアルバムであります。このアルバムの基調であるモッドなサウンドに対し根強く「本人たちはモッズじゃないのに商業的なモッズ戦略を行った」と非難される彼らですが、これに対し後にピート・タウンゼントはこう発言しています。「俺たちはモッズ出身のバンド見られたくて必死だった。気分は完全にモッズだった。このジャケットを見てくれれば分かるだろうけど、俺は生きてるだけで幸せだった。バンドにいて最高の気分だったんだ。」(レコードコレクター02年11月号より抜粋)。アルバムは1曲目の「Out
on the Street」からバンドの音が固まりになってぶつかって来ます。もうこの時点でキース・ムーンのドラムが「後のドラムンベースにまで影響あるんじゃないの?」と思えるほどグルーヴ感が出ており、特殊なものだと分かります。2曲目はアルバムで2曲(M2・8)も取り上げているジェームス・ブラウンのバラード。さすがにロジャーの歌はブラウンに及んでいませんが、それが逆に聴きやすさを醸し出しています。続く3〜5曲目まではピートによるコーラス重視ポップな小作が並ぶ。このポンポンと聴き易いポップ・ソングが出てくるあたりはやはりこのバンドが当時の他のモッド・バンドと比べ圧倒的に曲が書けるという事実を認識せずにはいられないでしょう。そして6・7曲目が永遠の青春アンセムである「My
Generation」と「The Kids Are Alright」の2曲。くるりの岸田繁氏が「ザ・フーってホントの意味で青春パンクだよなー」と言ってたのも頷ける完璧なまでに「俺ら主義(笑)」な歌詞。「My
Generation」はザ・フーならではの圧倒的な音圧とロジャーのたどたどしいヴォーカルが特徴的なザ・フーを代表する名曲。「The
Kids Are Alright」もメロディとコーラスとギターの絡みが思わずBeatlesを連想させるが、この曲に関してはBeatlesを遥かに凌いでおり、ザ・フー流ポップソングの完成形を提示している。9曲目は管理人が大のお気に入りナンバーである「It's
Not True」。ビーチ・ボーイズ好きで有名なキース・ムーンの要望に答えるかのようにピートが作り上げた全編フューチャーされるハーモニーが小気味良い2分半のポップソング。続くのが多くのモッド・バンドがカヴァーした古典的R&Bの名曲「I'm
a Man」。ロジャーの黒すぎないヴォーカルと後半に行くにしたがって凄まじいテンションに包まれていく演奏がやはり他のバンドとは一線を画している。稀代のセッション・ピアニストのニッキー・ホプキンスのピアノもガッチリ決まっている。12曲目はキース・ムーンのドラムが大フューチャーされる爆裂インスト「The
Ox」。やっとテンションを緩めた13曲目の「Circles」でようやくこのアルバムは終わる。全13曲若さと勢いと才能が大爆発した恐るべきこの名盤は後の音楽シーンの影響は計り知れないものがあり、今でもザ・フーが幾多のバンドからリスペクトされる由縁はすでにデビューアルバムからして確固たるものであったのです。